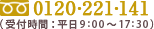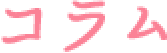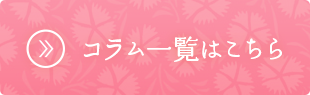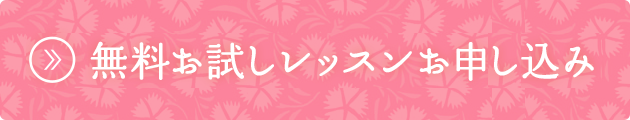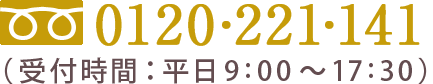「御召(おめし)」は着物通が好む魅力満載のお着物!

御召(おめし)の着物をご存じですか?
御召とは、正確には御召縮緬といいます。
訪問着や小紋といった着物の種類を指すのではなく、強撚糸を横糸に使い、先染めしてから織りあげた織物の種類のことを指します。
つるんとした仕上がりの絹織物とは違い、シボやシャリ感がある上質な風合いの生地に仕上がった絹織物の一種です。
江戸時代、江戸幕府11代将軍「徳川家斉」が愛用していたため「将軍様のお召し物」とされ、そこから武家や貴族の階級の人々が愛用し「高貴な位の方がお召しになる」といわれていたのが名前の由来です。
今でも後染めや紬などの着物よりも格上とされています。
今回は、「御召(おめし)」についてお話します。
お時間のある時にぜひご覧ください!
1.御召の技法と産地
糸同士を撚りあわせて作った糸を撚糸(ねんし)と呼びますが、御召にはこの撚りの回数を多くした「強撚糸(きょうねんし)」を横糸に使います。
これが生地の凹凸であるシボとシャリ感を生みます。
このようにして作る生地は、他には「縮緬(ちりめん)」があります。
また、「先染め(さきぞめ)」といって織る前に糸を染めるのも特徴です。
無地の御召は、生地のシボ感による陰影で立体感のある仕上がりが魅力です。
また、柄を生み出すためにあらかじめ計算して染め分けした糸を使った縞や格子や小紋などの御召は、柄とシボの組み合わせから柄に上品な奥行きが生まれます。
ちなみに大島などで有名な紬は、使用する糸の種類は違いますが、御召と同様の先染め技法で作られます。
有名な産地として、西陣御召(京都)、桐生御召(群馬)、塩沢御召(新潟)、白鷹御召(山形)などがあります。


2.御召のTPOと合わせる帯
御召は格上の着物ではありますが、それはあくまでも絹織物の格を指しています。
TPOは他の着物と同様に着物の種類、つまり柄ゆきで判断します。
無地の御召に刺繍紋があると略礼装になりますし、袋帯や織りの名古屋帯を合わせることで改まった装いとして着ることができます。
柄のある御召は、お洒落なお出かけ着として、または観劇や食事会、さほどフォーマルではないパーティなどに適しています。
希少ですが、御召の付け下げや訪問着もあります。
地模様が絵羽(生地が縦に縫い合わさった部分にかけて繋がって描かれている柄行き)になっているものは訪問着としてフォーマルで使うことができます。
最近は御召に後付けで柄を描いた付け下げや訪問着もあるようです。
御召に合わせる帯は一般の着物と同様です。
礼装用の御召には礼装用の帯を、普段着用の御召は普段着用の帯を合わせます。
いかがでしたでしょうか。
生地の風合いと深みのある仕上がり、そして着心地の良さから、御召は大変魅力的で着物通の方々から大変好まれています。
もしお手持ちのお着物の中に御召があったら、ぜひ着用してみてくださいね!
無料レッスンについて
きものレディでは無料お試しレッスンを開催しております。こちらからご応募ください。
ご不明点やご不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 写真映えする立ち方
- 歩き方や車の乗り降り
- お箸の持ち方
- 持っていると便利なグッズ
- お着物を汚した時の対処法
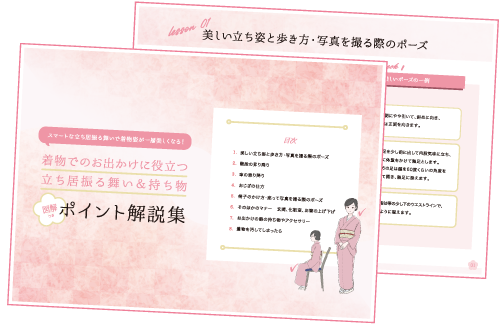
全ての教室が駅から5分以内の好アクセス